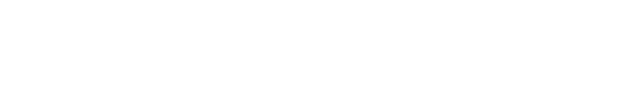☆在宅訪問医療を始める前に☆ -患者様、ご家族様へ-
、
当院は総合診療・救急・緩和ケアの専門家が幅広い病気に対応し在宅訪問診療を支えております。
※在宅訪問診療は定期契約の患者さまのみとなります
対象となる方
- 通院が難しい、外来の待ち時間が長くて大変な方
- 認知症や寝たきりの方
- ご家族の付き添いが大変な方
- 在宅で生活されるうえで医療のサポートが必要な方
- 入院せずに、ご自宅で治療を続けたい方
- ご自宅での終末期医療・緩和ケアをのぞむ方
- 退院後のご自宅での療養が不安な方
- いつでも気軽に相談できるかかりつけ医をお探しの方
- パーキンソン病や筋萎縮性側索硬化症など神経難病でお困りの方
- 独居高齢者の安否確認が必要な方
在宅医療において患者さんやご家族様に知っておいてほしいこと
在宅医療は、通院が困難で自宅での療養を希望される方々に向けて、医師や看護師がご自宅や老人ホーム、高齢者住宅を訪問して診療を行うものです。このサービスの大きなメリットは、患者さんが慣れ親しんだ環境で、よりリラックスして療養できることです。また、通院の負担が大幅に減ることも、患者さんやそのご家族にとって大きな利点です。
では、みなさんは、入院中の大切な家族が「家に帰りたい」と言ったとき、「じゃあ帰ろう」と安心して言ってあげられるでしょうか?
家族の希望を叶えてあげたい気持ちはあるけれど…
「今の家で本当に生活できるのかな…」 「もし急な事態が起きたらどうしよう…」 「一緒に住む家族はどう思うだろう…」 「これからの生活はどうなってしまうのか…」
そんな不安が次々に浮かんでくるのは当然のことです。自分たちの生活に大きく影響することだからこそ、心配になるのは無理もありません。
これらの心配の背景には、『どうすればいいか分からない』という不安があります。しかし、逆に言えば、『知識を持てば安心できる』ということです。
厚生労働省の受療行動調査によると、「自宅で療養できない」と回答した人が挙げた自宅療養を可能にするための条件トップ3は次の通りでした:
-
入浴や食事などの介護が受けられるサービス
-
家族の協力
-
療養に必要な用具(車いす、ベッドなど)
自宅療養が難しいと感じる方の多くは、在宅医療に関するサービス内容や相談先が分からないために不安を抱えているのではないでしょうか。
実は、在宅医療向けのサービスや制度は、思っている以上に整っており、利用しやすくなっています。訪問診療や看護、リハビリ、入浴のサービスがあり、バリアフリー改修の補助やベッドや車いすのレンタルも可能です。これらを知ってうまく活用することで、心配を減らし、大切な家族が安心して自宅での生活を送るお手伝いができます。
みなさんは、「自宅で介護を受けたい」と考えたことはありますか?内閣府の調査によると、多くの方が「自宅で最期を迎えたい」と思っているという結果が出ています。つまり、在宅医療は決して特別なことではなく、私たちの生活にとても身近な選択肢なのです。
ただ、「どれくらい費用がかかるのだろう?」と心配される方も多いでしょう。実際には、在宅医療には介護保険などのサポート制度があり、これらを活用することで費用の負担を軽減することができます。
大切な家族が快適に過ごせるように、そして介護する側も無理なくサポートできるように、在宅医療についての知識を持っておくことが大切です。ぜひ、この機会に在宅医療について理解を深めてみてください。
1. そもそも在宅医療ってなに?
在宅医療とは、通院が困難で自宅での療養を希望する患者さんのために、患者さんの自宅などに訪問して診療を行うことです。 「在宅」とは自宅はもちろん、老人ホームや高齢者住宅も含まれます。 患者さんにとっては通院の負担が減ったり、自宅という自由で安らげる環境に居られることがメリットです。医師が患者さんのところに訪問して治療を行うのですが、 どれくらいの頻度で訪問できるかというと 基本的には月2回(隔週)のところが多いです。このように定期的に訪問して診療を行うことを「訪問診療」と言います。 患者さんの状態が急変したり緊急に診てもらいたいことがあった場合、 患者さんからの要請で医師や看護師が駆けつけることを「往診」と言います。病院に入院している場合と同じように、困ったときにはお医者さんや看護師さんが来てくれる環境ならば、自宅にいても安心ですね。 しかし、自宅での診療よりも、日々の生活を不安に思う人の方が多いのではないでしょうか? 家族はどうやって生活すればいいの? 在宅医療を始めて介護することになったけれど、、、
「今まで介護なんてしたことがないからどうやっていいのか分からない・・・」
「本人の健康を保てるかな、満足してもらえるかな?・・・」
「すごく大変そうだから介護する側の時間がなくなって疲れてしまいそう・・・」
不安ですよね。 今までの日常生活になかった仕事が増えるのは事実です。 けれど、これを読まれている方は、 「自宅にいたいという本人の望みを叶えてあげたいから頑張りたい」 という気持ちがありますよね。 在宅医療をサポートするサービスはたくさんあります。
まずは、退院が決まったとき。 病院で行っていた医療を、在宅医療に変わっても続けられるように在宅医療に関わるスタッフと打ち合わせを行います。 そこで、日々の介護の方法を説明したり、訪問診療や訪問看護の日程を調整します。
在宅医療プランに納得し、在宅医療の生活を始めてみたら、 説明は受けたけど介護のやり方に不安が残る、入浴や食事の介助がうまくできなかったなど、やってみて分かる困ったことも出てくるかもしれません。 そういうときは「訪問看護」を利用すると良いでしょう。
訪問看護とは看護師さんが訪問して、医療・介護の両方から日常生活をサポートします。
病状の観察、薬の管理、入浴や食事の介助、排泄介助、介護の助言など、幅広く対応してもらえます。 他にも医師には相談しにくい悩みを聞いてくれたり、ときには雑談に乗ってくれたり・・・看護師さんはとても心強い存在です。日常生活での介護の心配を相談するところができるし、サポートをしてくれます。
でも、もっと介護しやすい環境にできないか、在宅だと筋力の衰えが気になると思われたら、「訪問リハビリ」があります。 訪問リハビリは理学療法士さん、作業療法士さんなどが訪問して、医師の指示に基づいて、患者さんが日常生活で自立できるように治療、訓練を行います。 介助方法の指導をしたり、手すりの設置や、介護用ベッドや車いすなどの福祉用具の相談にも対応します。 これで自宅環境の悩みも解決できそうですね
介護は毎日のこと、たまには自由時間が欲しい! どうしても外出しないといけない日もある。 そんなときは、「ショートステイ」や「介護ヘルパー」に頼るものいいと思います。
「訪問看護」「訪問リハビリ」、いずれにしても医師の指示が必要です。 在宅医療だからと頑張りすぎず、早めに医師や看護師さんに相談してくださいね。 その他のサービスも病院で紹介してもらえる場合があります。 直接は紹介できなくても、ケアマネジャーさんを紹介したり、どこに相談しに行けばよいかは教えてくれると思います。
2. 在宅医療にかかる費用はどのくらい?
在宅医療を初めて利用するとき、
「どのくらいお金がかかるのかな?」
「費用が高くなりそうで不安…」
と心配になる方もいらっしゃると思います。
実は、在宅医療にかかる費用は、保険が適用される場合が多いため、そこまで心配しなくても大丈夫です。ここでは、在宅医療で必要となる主な費用について、ご説明します。
在宅医療でかかる費用は、以下のように大きく分けられます。
1. 医療にかかる費用
医療保険が適用される場合が多いですが、以下のような費用が含まれます:
- 訪問診療代
- 検査や処置の費用
- 臨時の診療や往診費用
- 薬局で購入する薬代
これらは、医師が訪問して診察を行ったり、必要に応じた処置をした際にかかるものです。
訪問診療代と医療費・薬代
在宅医療でかかる医療費や薬代は、通院や入院の場合と同じように医療保険が適用されます。自己負担の割合は以下の通りです:
- 75歳以上:1割負担(※現役並み所得者は3割)
- 70~74歳:2割負担(※現役並み所得者は3割)
- 70歳未満:3割負担
さらに、月の自己負担額が一定額(自己負担限度額)を超えた場合、申請すると払い戻される高額療養費制度も利用できます。
訪問診療代の目安
支払額(負担額)は、診療内容や年齢によって異なりますが、1割負担の方の場合:
- 月2回の定期訪問診療で6,500~12,000円程度(その他費用を除く)
自己負担限度額の例
例えば、70歳以上の一般所得者の場合、自己負担限度額は月18,000円です。この仕組みを活用すれば、在宅医療の負担を大幅に軽減できます。
2. 介護にかかる費用
在宅医療では医療費だけでなく介護費用もかかる場合があります。
ですがご安心ください!医療保険や介護保険、さらに公的な支援制度などを利用することで、これらの費用が高額になりすぎないような仕組みがしっかりと整っています。
お困りの際は、医療機関やケアマネージャーさんにぜひご相談くださいね。
在宅医療を受けているほとんどのご家庭では、多彩な介護サービスも併せて利用されています。
介護サービスは、介護保険を利用して受けることができます。サービスを利用するには、要介護認定を受ける必要があり、認定された介護度(要支援1~要介護5)によって、支給限度額や受けられるサービス内容が決まります。
介護保険が適用されることが多いサービスです
- 訪問看護、訪問介護
- 訪問リハビリ、訪問入浴介護
- 居宅療養管理指導
- デイサービスやショートステイ
- 福祉器具のレンタル
これらは、日常生活をサポートするために必要なサービスで、内容に応じて費用が異なります。
支給限度額の目安
例として、支給限度額は以下の通りです:
- 要支援1(最も軽度):月50,030円
- 要介護5(最も重度):月362,170円
この範囲内であれば、利用者の負担は原則1割(年齢や所得に応じて2~3割)です。
支給限度額を超えた場合は?
支給限度額を超えてサービスを利用した場合、その超過分は全額自費となります。たとえば、リハビリや訪問介護を追加で多く受けたい場合などが該当します。
介護サービスをどのように利用すればよいか迷ったときは、ケアマネージャーさんや医療機関にお気軽にご相談くださいね。
3. その他の費用
介護や医療の内容によって必要になる、以下のような費用も考えられます:
- 食費や栄養剤代
- 住宅のリフォーム費用(バリアフリー化など)
- 消耗品(おむつや消毒用品など)の購入費用
- 光熱費(在宅医療機器の使用が増える場合など)
福祉器具のレンタルや購入・住宅改修費(介護リフォーム代)
- ベッドや車いすなど、介護保険を利用してレンタルや購入が可能です。
- トイレの手すり設置や段差解消などの改修費用に、上限20万円まで補助金が支給されます。
- これらの費用は、他の介護保険サービスの支給限度額には含まれません。
費用の総額は?サービス選びは専門家と相談を
在宅医療にかかる費用は、患者さんの状態や必要な介護内容によって異なりますが、入院よりは安い場合が多いです。負担を軽減する制度も活用しましょう。
詳しい内容や手続きについては、自治体の相談窓口、医療ソーシャルワーカーさん、またはケアマネジャーさんにお気軽にご相談ください。ケアマネジャーさんはどのサービスが必要か迷うとき、あなたの状況に合った最適なサービスを提案してくれますよ。
3. 在宅医療を始める前に確認しておきたいこと
ここまで在宅医療について前向きなお話をしてきましたが、一度立ち止まって、大切なことを確認してみましょう。
ご本人とご家族の気持ち
在宅医療は、ご本人が「自宅で過ごしたい」という希望を叶えるためのものです。しかし、その実現にはご家族の協力が欠かせません。
ご家族が無理をして生活に支障が出たり、体調を崩してしまうと、在宅医療そのものが難しくなることがあります。
また、ご家族が辛そうな様子を見てしまうと、ご本人は「申し訳ない」と責任を感じてしまうかもしれません。
だからこそ、ご本人の気持ちとご家族の負担のバランスを取ることがとても大切です。
不安があれば一人で抱え込まず相談を
在宅医療を始めることに不安や迷いがあるのは自然なことです。そんなときは、身近な医療関係者にどんどん相談してください。
医師、看護師さん、ケアマネジャーさん、ソーシャルワーカーさんなど、支えてくれる人はたくさんいます。不安な気持ちを伝えることで、一緒に解決策を見つけることができます。
「まずやってみる」から始めてみませんか?
在宅医療は、「ご本人の希望を叶えてあげたい」という気持ちからスタートしてみるのも一つの方法です。
実際に始めてみて難しいと感じたら、そのときに次の選択肢を考えれば大丈夫です。
在宅医療は、家族が助け合うことで絆を深める機会にもなります。無理をしすぎず、周りのサポートを活用しながら、家族みんなで一緒に考えていきましょう。
4. 在宅医療を始めるための手続き
在宅医療を始めるには、いくつかの手順が必要です。ここでは、その流れを簡単にご説明します。
1. 在宅主治医を選びましょう
まずは、在宅医療を担当してくれる在宅主治医を決めます。
- 現在かかっている医師に相談して紹介を受ける。
- 入院中の方は、病院の地域医療連携室で医療ソーシャルワーカーに相談する。
2. 介護保険の準備をしましょう
在宅医療には、介護保険が大切なサポートになります。ただし、すぐに使えるわけではありません。
- お住まいの市区町村に要介護認定の申請を行いましょう。
- 認定が下りるまでに1ヵ月ほどかかるので、早めの準備がおすすめです。
3. ケアマネジャーさんとケアプランを作成
ケアマネジャーさんは、在宅医療や介護をサポートする計画(ケアプラン)を作成するパートナーです。
- ケアマネジャーさんと相談して、必要な介護サービスを決めていきます。
- ケアマネジャーさんとは長いお付き合いになります。親身になってくれる、信頼できる人がおすすめです。
4. 在宅主治医と病院の連携
病院から在宅主治医へ、患者さんの診療情報提供書を依頼します。その後、在宅医療に関わるスタッフが連携をとり、医療方針や訪問日時などを決定します。
5. 在宅医療のスタート
これで準備が整えば、いよいよ在宅医療が始まります!
5. さいごに
旅行から帰ってきたとき、つい「やっぱり家が一番落ち着く」と感じたことはありませんか?
それがもし入院生活なら、「自宅に帰りたい」と思うのは自然なことです。
でも、在宅医療を始めるとなると、
「自分に介護ができるだろうか?」
「負担が大きすぎないだろうか?」
と、不安に感じる方も多いですよね。
不安を解消するために
ご安心ください。在宅医療には、その不安を支える仕組みやサービスがしっかりと用意されています。
私が担当したご家族の中にも、最初は戸惑いや不安でいっぱいだった方がたくさんいらっしゃいました。
しかし、具体的なサポート内容を説明すると:
「それならやってみようかな」
と思い直し、実際に始めてみると「思った以上にできている」と感じられるケースが多いのです。
解決策を探して一歩踏み出そう
在宅医療においては、マイナス面ばかりに目を向けるのではなく、その問題をどう解決できるかを考えることが大切です。
医師、看護師さん、ケアマネジャーさんなど、頼れる人はたくさんいます。不安や疑問があれば、どんどん相談してくださいね。
自宅で過ごす時間の特別さ
自宅は、患者さんにとってもご家族にとっても、特別で落ち着ける空間です。そこで一緒に過ごす時間は、何ものにも代えがたいかけがえのないものです。
その素敵な時間を大切にするために、しっかり知識を蓄えて、準備を整えていきましょう。
在宅医療が、皆さんの家族にとって温かく豊かな時間を生み出すきっかけになることを願っています。
はやぶさ内科ホームクリニック 院長 山口 隼